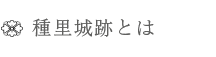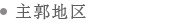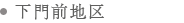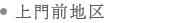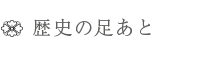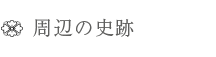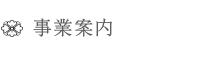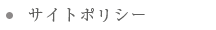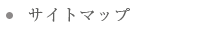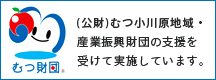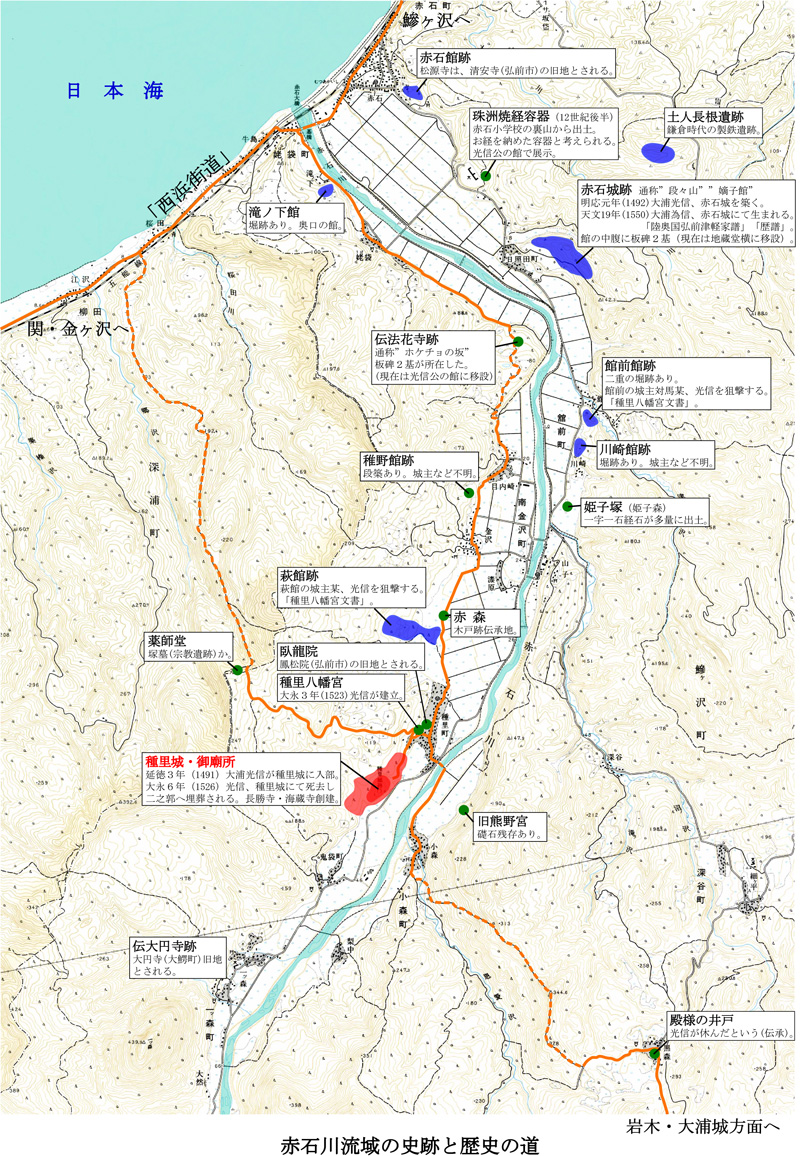種里城跡は、世界自然遺産「白神山地」を源流として、日本海に流れ出る赤石川の流域にあります。その周辺には、大浦光信や津軽藩発祥にまつわる史跡や伝承地、光信の入部前にさかのぼる安藤氏時代の板碑など、豊かな歴史・文化遺産が残されています。
史跡個別紹介
-
*画像クリックで拡大します
 種里城跡
種里城跡
-
 有原遺跡
有原遺跡
-
 有原館跡
有原館跡
-
 堤ノ沢館跡
堤ノ沢館跡
-
 萩館跡
萩館跡
-
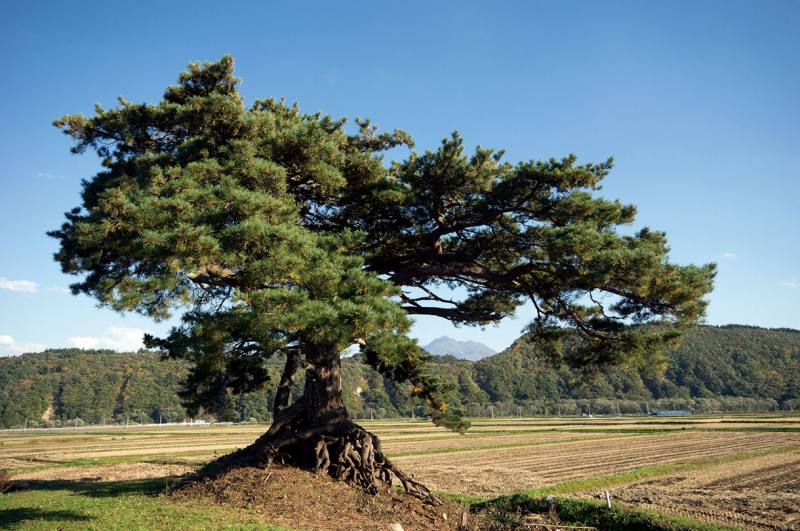 赤森
赤森
-
 稚野館跡
稚野館跡
-
 滝ノ下館跡
滝ノ下館跡
-
 川崎館跡
川崎館跡
-
 館前館跡
館前館跡
-
 赤石城跡
赤石城跡
-
 赤石館跡
赤石館跡
-
 土人長根遺跡
分類:遺跡
土人長根遺跡
分類:遺跡
解説:大和田川上流の山中で発掘調査された鎌倉時代の製鉄遺跡。製鉄炉・廃滓場・炭窯跡などが見つかっている。大浦光信の入部する前、安藤氏が大規模な鉄生産に関わっていた可能性が考えられている。
所在地はこちら -
 種里八幡宮
種里八幡宮
-
 薬師堂
薬師堂
-
 臥龍院
臥龍院
-
 松源寺
分類:社寺
松源寺
分類:社寺
解説:天正2年(1574)に長勝寺3世蜜田和尚の隠居所として松源院が建立され、弘前城築城とともに弘前城下に移って清安寺となった。その後、承応年間(1652~1655)に創建されたのが現在の松源寺とされる。曹洞宗。
所在地はこちら -
 伝長勝寺跡
伝長勝寺跡
-
 伝金剛寺跡
伝金剛寺跡
-
 伝大円寺跡
伝大円寺跡
-
 伝法花寺跡
分類:社寺
伝法花寺跡
分類:社寺
解説:姥袋集落から目内崎集落への山道沿いに「法花寺」の地名があり、坂道を「ホケチョの坂」といった。南北朝時代の板碑2基があったが、その後牛島の共同墓地に移され、現在は光信公の館に移設されている。
所在地はこちら -
 種里旧墓地の板碑
分類:板碑
種里旧墓地の板碑
分類:板碑
解説:種里集落裏の旧墓地にある。板碑の造立には南北朝時代の安藤氏が関わったとみられている。大浦光信の入部する前、種里は安藤氏の勢力下にあった可能性が考えられる。鰺ヶ沢町指定文化財。
所在地はこちら -
 日照田地蔵堂の板碑
分類:板碑
日照田地蔵堂の板碑
分類:板碑
解説:日照田集落の地蔵堂横に2基の板碑があり、うち1基に応安8年(1375)の年号が確認できる。板碑の造立には南北朝時代の安藤氏が関わったとみられている。鰺ヶ沢町指定文化財。
所在地はこちら -
 日照田一本松の板碑
日照田一本松の板碑
-
 松源寺の板碑
松源寺の板碑
-
 光信公御廟所
分類:その他
光信公御廟所
分類:その他
解説:大永6年(1526)10月8日に死去したとされる大浦光信の墓所。傍らには殉死した家臣・奈良主水貞親(種里八幡宮初代宮司)が葬られたとされる。津軽氏の聖地として顕彰されてきた。
所在地はこちら -
 種里城址碑
種里城址碑
-
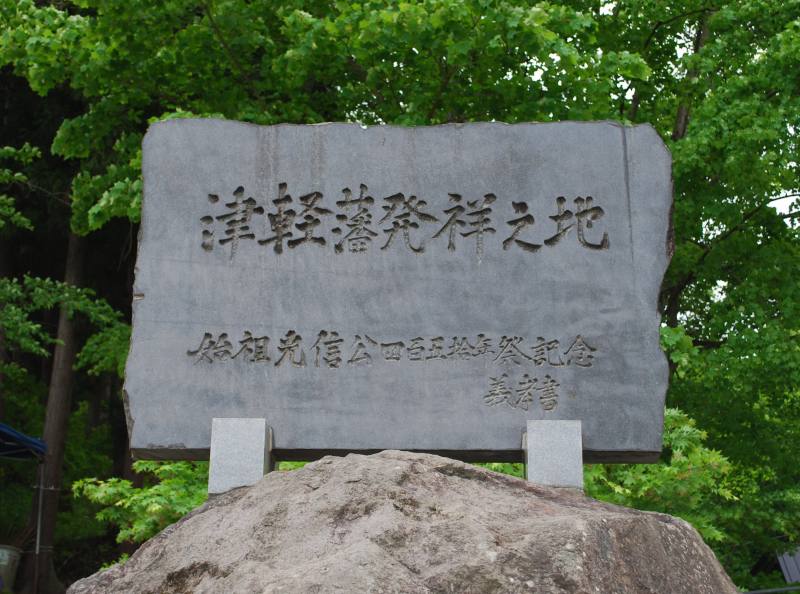 津軽藩発祥之地碑
津軽藩発祥之地碑
-
 海蔵寺開創の地碑
分類:その他
海蔵寺開創の地碑
分類:その他
解説:昭和57年(1982)9月7日に海蔵寺33世により種里集落内に建立された。海蔵寺は明応元年(1492)に大浦光信が菩提寺として種里に創建したとされる。その後は大浦城下に、さらに弘前城下に移った。曹洞宗。
所在地はこちら -
 ハタフグの松
分類:その他
ハタフグの松
分類:その他
解説:種里八幡宮裏の山道沿いにあり、大浦光信の軍勢が旗や鉾を立てかけて休んだ場所と伝えられる。ハタホコ(旗鉾)が転訛したのが地名の由来と考えられている。種里八幡宮文書では、この道は大浦光信が新たに切り開いた道とされている。
所在地はこちら -
 殿様の井戸
分類:その他
殿様の井戸
分類:その他
解説:黒森集落内にあり、大浦光信が休んだ井戸水と伝えられる。光信の時代、種里城→小森→黒森を通って岩木山の裏手をまわり、大浦城、津軽平野に出る山道が用いられていたと考えられている。
所在地はこちら -
 姫子塚
姫子塚
-
 珠洲焼経容器
珠洲焼経容器
-
 大和田出土埋蔵銭
分類:その他
大和田出土埋蔵銭
分類:その他
解説:大和田川河口の砂丘地から昭和40年代頃に偶然発見された。総数1万枚以上にも及ぶ中国・朝鮮・琉球からの渡来銭であるが、国内で作られた中国銭の模鋳銭も含まれている。埋められた時期は、16世紀前半頃と推定されている。
所在地はこちら