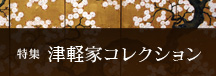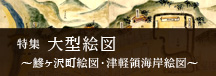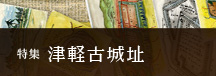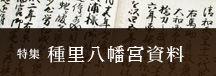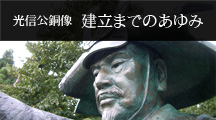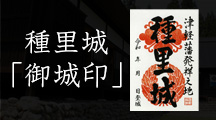収蔵品ギャラリー
時代・年代別【近代】
40件中 21-40件を表示中
*画像はクリックすると拡大します
-

- 台帳No.22工藤晴好筆「雪中漁舎図」
-
時代・年代 近代 分類 01絵画 寄贈者 - サイズ 200.5cm×42.5cm - 工藤晴好(1867~1924)は深浦町出身の日本画家。本名、相馬タケ。明治18年(1885)同じ日本画家の工藤仙来と結婚。仙来没後上京し奥原晴湖の塾に入門、晴湖の養女晴翠に学ぶ。師の一字をとって晴好と号した。
-

- 台帳No.39野沢如洋筆「山水図」
-
時代・年代 近代 分類 01絵画 寄贈者 - サイズ 193cm×47cm - 野沢如洋(1865~1937)は弘前生まれの日本画家。明治期の青森県の画家の中で、国が主催する日本画の展覧会をはじめとする多くの展覧会に出品し、上位の賞を得た画人であった。山水画の達人として知られ、本作もすぐれた作品の一つである。
-

- 台帳No.77野沢如洋筆「山水図」
-
時代・年代 近代 分類 01絵画 寄贈者 - サイズ 192.5cm×54cm - 野沢如洋(1865~1937)は弘前生まれの日本画家。明治期の青森県の画家の中で、国が主催する日本画の展覧会をはじめとする多くの展覧会に出品し、上位の賞を得た画人であった。山水画の達人として知られる。
-

- 台帳No.140-2野沢如洋筆「山水図」
-
時代・年代 近代 分類 01絵画 寄贈者 - サイズ 217cm×79cm - 野沢如洋(1865~1937)は弘前生まれの日本画家。明治期の青森県の画家の中で、国が主催する日本画の展覧会をはじめとする多くの展覧会に出品し、上位の賞を得た画人であった。山水画の達人として知られる。
-

- 台帳No.140-3野沢如洋筆「山水図」
-
時代・年代 近代 分類 01絵画 寄贈者 - サイズ 217.5cm×67cm - 野沢如洋(1865~1937)は弘前生まれの日本画家。明治期の青森県の画家の中で、国が主催する日本画の展覧会をはじめとする多くの展覧会に出品し、上位の賞を得た画人であった。山水画の達人として知られる。
-

- 台帳No.134須藤聖馬筆「馬図扇」
-
時代・年代 近代 分類 01絵画 寄贈者 - サイズ 29cm×48.5cm - 須藤聖馬(1900~?)は弘前生まれの日本画家。近代山水画の達人とされる野沢如洋に師事。馬を描いた優品で知られる如洋にならい、注目される作品を残した。
-

- 台帳No.119寺島春堂筆「雪景図」
-
時代・年代 近代 分類 01絵画 寄贈者 - サイズ 223.5cm×58cm - 寺島泉岱(1867~?)は弘前生まれの日本画家。春堂も画号の一つ。三上仙年に師事。花鳥、山水、人物と広範囲にわたる作品がある。
-

- 台帳No.135寺島春童筆「花鳥図」
-
時代・年代 近代 分類 01絵画 寄贈者 - サイズ 192.5cm×74.5cm - 寺島泉岱(1867~?)は弘前生まれの日本画家。春童も画号の一つ。三上仙年に師事。花鳥、山水、人物と広範囲にわたる作品がある。
-

- 台帳No.74佐藤禅忠筆「寒山拾得図」
-
時代・年代 近代 分類 01絵画 寄贈者 - サイズ 222cm×54.5cm - 佐藤禅忠(1799~1878)は弘前生まれの名僧、鎌倉の東慶寺住職、禅画の大家。大正12年(1923)の関東大震災で東慶寺が全壊すると、これの復興と布教に努めた。特に青森県内をはじめ北海道の各地の布教は精力的なものであった。今日津軽地方に残る画像はこの時のものが多い。
-

- 台帳No.141蔦谷龍岬筆「江水遊船図」
-
時代・年代 近代 分類 01絵画 寄贈者 - サイズ 224cm×42.5cm - 蔦谷龍岬(1886~1993)は弘前生まれの日本画家。明治35年(1902)上京して日本画壇に名を著した。津軽で直接筆をとる機会が少なかったこともあり、龍岬の作品は青森県内には比較的少ないとされる。
-

- 台帳No.52海浦義観筆「釈迦説法図」
-
時代・年代 近代 分類 01絵画 寄贈者 - サイズ 197.5cm×44.5cm - 海浦義観(1855~1921)は深浦町円覚寺26世住職。わが国で最初の修験道についての概説書を著した。本作は仏画にも優れていた義観を偲ばせる作品である。
-

- 台帳No.132荒木十畝筆「梅に鳥図」
-
時代・年代 近代 分類 01絵画 寄贈者 - サイズ 146.5cm×71cm - 荒木十畝(1872~1944)は長崎県生まれの日本画家。近代日本画壇を率いた人物の1人であり、花鳥画を得意とした。
-

- 台帳No.133野沢如洋筆「松竹梅図屏風」
-
時代・年代 近代 分類 02屏風 寄贈者 - サイズ 175.5cm×178cm - 野沢如洋(1865~1937)が描いた2曲半双の屏風。如洋は弘前生まれの日本画家。明治期の青森県の画家の中で、国が主催する日本画の展覧会をはじめとする多くの展覧会に出品し、上位の賞を得た画人であった。
-
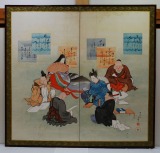
- 台帳No.175-1寺島春童筆「六歌仙図屏風」
-
時代・年代 近代 分類 02屏風 寄贈者 - サイズ 165.5cm×174.5cm - 寺島泉岱(1867~?)が描いた2曲1双の屏風(右隻)。泉岱は弘前生まれの日本画家。春童も画号の一つ。三上仙年に師事。花鳥、山水、人物と広範囲にわたる作品がある。
-

- 台帳No.175-2寺島春童筆「六歌仙図屏風」
-
時代・年代 近代 分類 02屏風 寄贈者 - サイズ 165.5cm×174.5cm - 寺島泉岱(1867~?)が描いた2曲1双の屏風(左隻)。泉岱は弘前生まれの日本画家。春童も画号の一つ。三上仙年に師事。花鳥、山水、人物と広範囲にわたる作品がある。
-

- 台帳No.174松山玉泉筆「花鳥図屏風」
-
時代・年代 近代 分類 02屏風 寄贈者 長尾匡士 サイズ 172.5cm×353.5cm - 松山玉泉(1857~1944)が描いた6曲半双の屏風。玉泉は鰺ヶ沢町米町の絵師。本名、文策。表具師を業としていたので絵に興味を抱き、18歳で津軽狩野派の継承者・外崎則清と弟の鶴幼に絵を学ぶ。のち、藩抱絵師・新井家7代目勝峰に師事した。
-

- 台帳No.27島川観水筆「鳥啼山更幽」
-
時代・年代 近代 分類 03書跡 寄贈者 - サイズ 204.5cm×41cm - 島川観水(1881~1943)は深浦町秋田屋に生まれた。本名、久一郎。上京して日本時計商工新聞社を創設、社長となって徳富蘇峰、孫文らと交わった。各地の音頭や小唄の作詞のほか、俳句、漢詩なども得意な多才な文化人であった。
-
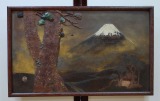
- 台帳No.138工藤仙来作「岩木山図」(破笠細工)
-
時代・年代 近代 分類 04工芸 寄贈者 - サイズ 49.5cm×80cm - 破笠細工とは漆芸技法の一つで、漆器に貝、金属等を蒔絵と併用して文様を表したもの。江戸中期の漆芸家・小川破笠(1663~1747)が得意としたところから名づけられた。破笠は享保8年(1723)、60歳のときに5代藩主信寿に江戸で細工人として召し抱えられた。津軽において、この破笠の技法を受けついだ者は無いが、のちに工藤雲崖とその子仙来が影響を受けたとされる。本作は工藤仙来(1863~1944)の作。
40件中 21-40件を表示中