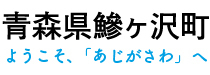介護サービス利用のながれ
更新日:2025年6月4日
問題なくできていた食事の準備・掃除やお風呂・トイレなど毎日の生活動作などが、病気・けが・認知症などをきっかけにできなくなったりします。介護や支援が必要かなと思ったら、1日の暮らしの中で、何ができて何ができないのかを書き出してみましょう。
どうやったら介護サービスを利用できるの?
介護や支援が必要になったときに介護サービスを利用するには、要介護・要支援認定を受けることが必要です。要介護・要支援とは、日常生活の中でどの程度の介護(介助)を必要とするのかという介護の必要度合いを判断するためのものです。
要介護・要支援認定を受けるには、申請手続きをしていただく必要があり、申請ができるのは下記の1か2のいずれかの方です。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)で下記の16種類の特定疾病のいずれかに該当する方
・がん (医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
どのような介護サービスがあるの?
介護サービスには、自宅等で受けられるサービス、自宅から通って受けられるサービス、施設に入居するサービスなど、様々な種類があります。また、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっています。
具体的なサービスの内容については、こちらのページをご覧ください。
(介護保険で利用できるサービス27種類を掲載していますが、当町は介護資源(施設や人材)が不足しており、掲載している全てのサービスが提供されていませんので、あらかじめご了承ください。)
相談・申請は、どこでできるの?
役場庁舎1階(1番窓口)にある「介護保険担当窓口」または「地域包括支援センター」にご相談ください。
申請は本人のほか家族もできます。また、地域包括支援センターや成年後見人、居宅介護支援事業者や介護保険施設等に代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
・要介護(要支援)認定申請書(申請書様式は「申請書類等ダウンロード」ページをご覧ください)
※申請書は、役場の介護保険担当(庁舎1階・1番窓口)にもあります。
・介護保険被保険者証
・健康保険証
申請したあとは、どのような手続きがあるの?
申請すると、町の職員等が自宅等へ訪問して行われる「認定調査」と、かかりつけ医による「意見書の作成」が行われます。
その後、この2つの結果に基づくコンピュータによる「一次判定」、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による「二次判定」を経て、要介護状態区分(要介護度)が決定されます。
通常、介護申請から結果通知まで30日程度かかります。
要介護度の目安は?
介護の必要度により、非該当(自立)、要支援(1から2)、要介護(1から5)の8つの段階に分けられています。「要支援」や「要介護」は、日常生活の中でどの程度の介護(介助)を必要とするのかという介護の必要度合いをあらわすものです。段階により利用できるサービスや支給限度基準額が変わってきます。
| 要介護度 | 状態 |
|---|---|
| 自立 | 家事や身の回りのことなどが可能で、一人で生活でき、介護や支援を必要としていない状態 |
| 要支援1 | 日常生活上の動作はほぼ自立しており、基本的には一人で生活できるが、現在の状態が悪化しないように支援が必要である状態 |
| 要支援2 | 基本的には一人で生活できる状態だが、要支援1と比較すると自分でできることが少なくなり、日常の複雑な動作には介助を必要とする場面が多くなる |
| 要介護1 | 基本的には一人で生活できるが、要支援2と比較すると運動機能の低下や、思考力・理解力の低下、問題行動がみられることがある
|
| 要介護2 | 食事や排せつなどの基本動作でも部分的な介助が必要となり、要介護1よりも思考力や理解力の低下、問題行動などがみられる
|
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行が困難となるなど全面的な介助が必要となり、思考力や理解力の低下、問題行動がみられ日常生活に影響がでてくる
|
| 要介護4 | 立ち上がりや自力歩行がほとんどできないなど全面的な介助が必要で、要介護3と比較して思考力や理解力の低下、問題行動などがみられる
|
| 要介護5 | 寝たきりなどで介護なしでは生活できない状態で、意思疎通が困難となる
|
一人ひとりの状態が異なるため、あくまでも参考としてご覧ください。
要介護状態区分が判定されたあとは?
まずは、サービスの利用開始にむけて「ケアプラン」を作成しますが、どこで生活するのか(自宅か施設入所か)、本人の状態(要介護か要支援か)によって、手続きが違います。本人や家族にとって本当に必要なケアプランを作成するためには、ケアマネジャーなどの専門家のアドバイスはもちろんですが、「こんな生活を送りたい」「こんなことができるようになりたい」という利用者自身の希望や目標をきちんと伝え、ケアプランに反映してもらうことが大切です。
また、サービスを利用してからも、定期的にチェックして、不都合な点やサービスの内容で困ったことがあったらケアマネジャーなどに相談して改善してもらいましょう。
要介護1から5と認定され、自宅でサービスを利用したいかた
- ケアマネジャーを決定します
事業者一覧の中から「居宅介護支援事業者」を選び、連絡してください。担当するケアマネジャーが決まります。ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護を必要とする方が介護保険サービスを受けるにあたって、サービス事業者との調整を行う介護保険に関するスペシャリストです。
- ケアプランを作成します
自分が「どのような介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」について、担当するケアマネジャーと話し合いながらケアプランを作成します。
※ケアプラン作成のための費用は、無料です。
- サービスを利用します
サービス事業者と契約します。作成したケアプランにそって、サービスを利用します。
要介護1から5と認定され、施設に入所したいかた
- 入所したい施設に連絡します
実際に見学したり、サービス内容や利用料を検討したうえで施設に申し込みます。
- ケアプランを作成します
入所した施設のケアマネジャーとケアプランを作成します。
- サービスを利用します
作成したケアプランにそって、サービスを利用します。
要支援1・2と認定されたかた
- 地域包括支援センターに連絡します。
地域包括支援センターに相談し、自分が「どのような生活をしたいか」を伝えます。
- ケアプランを作成します
担当する職員と話し合い、サービス内容を検討し、ケアプランを作成します。
※ケアプラン作成のための費用は、無料です。
- サービスを利用します
サービス事業者と契約します。作成したケアプランにそって、サービスを利用します。
サービス事業所を選ぶにあたって
- 介護サービス情報公表制度
事業所の概要やサービス内容、利用料金などの情報が公表されています。介護サービス事業所を選ぶときの参考としてください。![]() 青森県「介護サービス情報公表システム」のページへ(外部サイト)
青森県「介護サービス情報公表システム」のページへ(外部サイト)
- 地域密着型サービスの自己評価及び外部評価について
認知症高齢者グループホームは、自己評価及び外部評価が義務づけられ、評価結果がWAM NET(独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保険・医療の総合情報サイト)に公表されています。![]() WAM NET「介護保険地域密着型サービス外部評価情報」のページへ(外部サイト)
WAM NET「介護保険地域密着型サービス外部評価情報」のページへ(外部サイト)
有効期間が過ぎる前に
認定の有効期間は原則6か月(更新認定の場合、本人の状態に応じて最長36か月)です。
有効期間が近づいた方には、更新のための申請書を送付しています。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に申請書を提出してください。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了の60日前から受け付けます。